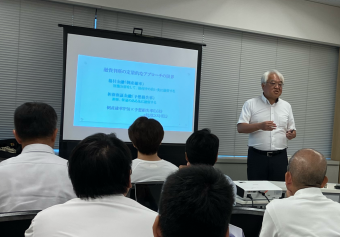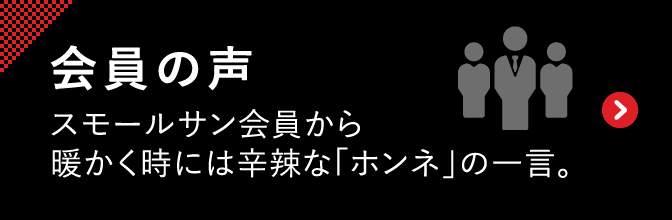<
山口恵里の“現場に行く!”2025年10月号
「第71回:ゼミTOKYOレポート〜『人と絆の金融』〜」
皆さん、こんにちは!スモールサン事務局の山口恵里です。
今月の「山口恵里の“現場に行く!”」は、8月に開催されたスモールサン・ゼミTOKYOの模様をレポートします!
スモールサン・ゼミは、全国各地で毎月1回、年12回開催されている中小企業経営者のための勉強会です。毎月専門家の講師を招き、中小企業の経営課題を解決するためのヒントや実践的な学びを得るだけでなく、ゼミ生同士が交流し、仲間として連携したり切磋琢磨できる場としても大切にされています。
今回はその中からゼミTOKYOの様子をお届けすると共に、8月講師としてお招きしていた元第一勧業信用組合理事長で、開智国際大学客員教授、笑顔のコミュニティー会社会社代表の新田信行氏による講演「人と絆の金融」もレポートしたいと思います!
スモールサン・ゼミTOKYOとは 〜経営者が主体的に関わり共に学ぶ場〜
スモールサン・ゼミは、全国で地域ごとに運営され、現地の経営者が運営に携わることで自分達に必要な学びを主体的に取り入れています。それにより、それぞれのゼミが独自のカラーを持ちながら、「中小企業を強く元気にする!」という共通の理念のもとに活動しています。
その中でもゼミTOKYOは、首都圏の経営者や専門家が集う場として最初に開設されたゼミです。様々な試行錯誤をしながら長年運営され続け、今年で17期目。スモールサン・ゼミは18時30分からのスタートが多いのですが、前期では試験的に15時から始めるというチャレンジもしていました。その結果少し早すぎるということで、今期は16時からになっています。自分達が学ぶ場としてこうした試行錯誤ができるのもスモールサン・ゼミの特徴の一つです。
ゼミTOKYOでは、勉強会の冒頭で「GOOD&NEW」と呼ばれるセッションが行われます。メンバーがいくつかのグループに分かれ、それぞれが最近の「良かったこと」と「新しい出来事」を短く報告し合います。
この日は「家族旅行で四国を巡り、ポケモン電車やフェリーを楽しんだ」「お盆休みに岩手で大谷翔平の田んぼアートを見て元気をもらった」といったプライベートの話題から、「効率化によって利益率が改善し、決算賞与を出せそうだ」といった経営上の成果まで、さまざまな報告がされました。小さな喜びや成果を共有し合うこの時間は、会場の雰囲気を温めるだけでなく、互いの挑戦や努力を知る貴重な機会となっています。
加えて、このアイスブレイクでは、毎月配信しているスモールサン・ニュースの『景気を読む』を題材に軽い意見交換も行っています。この時期はやはりトランプ関税の不透明さが話題の中心になり、「情報を鵜呑みにせず、自ら学び続けることが重要」「何が起こるか分からないからこそ、自社の体力をつける必要がある」と改めて認識を深目ました。
自社発表から広がる学びと共感

さらにゼミTOKTOでは、ゼミ生による「自社発表」の機会も設けられています。自社の事業や取り組みを発表することで自社を客観的に見直すきっかけになり、また日頃詳しく聞く機会のないメンバーの事業について知る機会になります。
この日の自社発表を担当したのは、株式会社クニイ代表取締役の木村 達也さん。スモールサン・ゼミへの参加は、現在ゼミTOKYOの担当プロデューサーになっている滝瀬さんの紹介がきっかけだといいます。
今回の発表では、グループ会社の日本メガケアの事業から説明がありました。病院で使用される医療用酸素の供給を担う同社は、コロナ禍でパルスオキシメーターの需要が急増し、酸素の供給が社会的使命と直結することを改めて実感したといいます。一方で酸素の薬価は国によって一律に定められており、仕入れ価格が上昇しても販売価格には転嫁できない構造的な厳しさも抱えています。
木村さん自身は、日本メガケアに入社した当初、医療ガス設備工事の現場で右も左も分からない状態からのスタートでした。現場に入り、理不尽な要求を受けることも少なくなかったと振り返りますが、その経験が結果的に自分を鍛え、独立心と判断力を育ててくれたと語りました。そうした経緯を経て、5年前にクニイの代表に就任。日本メガケアとしては初の新規事業として空調事業を立ち上げ、クニイをグループの子会社化するという大きな決断を実行しました。
就任当時「中はしっちゃかめっちゃかで、今にも潰れそうな状態」だったといいます。しかし木村さんは思い切って経営改革に着手しました。「失うものはない。やって駄目ならまた考えればいい」と挑戦を重ねた結果、少しずつ業績は改善されてきました。現在は、既存の取引先で空調設備の仕事を受注しつつも、そこに依存するのではなく、日本メガケアが持つ病院ネットワークを活かした新しい展開に挑戦しているとのこと。酸素という主力分野が価格規制で利益を出しにくくなる一方で、病院に必ず備わる空調設備には確かな需要があり、グループ全体のシナジー効果を生み出せる可能性があります。
木村さんは「最後はクニイを自立した会社として残し、見届けたい」と力強く締めくくりました。
「人と絆の金融」 〜新田信行氏の問題提起〜
さて、自社発表の後はいよいよ講師の講演です。
8月の講師は、元第一勧業信用組合理事長で、開智国際大学客員教授、笑顔のコミュニティー会社会社代表の新田信行氏。講演テーマは、4月に上梓された自身の著書のタイトルでもある「人と絆の金融」。
講演の冒頭、新田氏は「金融とは本来、人と人、企業と社会をつなぐ“絆”をつくるもの」と語りました。金融機関に長く身を置き、地域金融や中小企業支援に深く携わってきた新田氏だからこそ、その言葉には重みがあります。
「資金を貸し出すだけが金融ではありません。目先の数字や担保だけを見るのではなく、経営者の思いや、そこに働く人々の力、地域社会との関わりを踏まえてこそ金融の役割は果たされるのです。」
新田氏は、現在の金融の大きな課題として“点数主義”を挙げました。財務諸表や格付けといった数値に頼りすぎるあまり、企業の未来を見抜く目を失っているのではないかと指摘します。「決算書に載っているのは過去に採れたリンゴ。私たちが本当に知りたいのは『来年リンゴがいくつ採れるか』です」という言葉がとても印象的でした。
バブル崩壊後、銀行は不良債権処理に追われ、数値による厳格な評価を強めました。確かに「数字に基づく客観性」は必要ですが、その一方で数字での評価が難しい部分は軽視され、その結果、潜在力のある中小企業がその力を十分に活かせないまま淘汰されるケースも少なくありませんでした。
新田氏は「雨が降ったら傘を取り上げるのが今の格付け金融」と表現します。そのうえで、「銀行が本当に見るべきは、経営者の目の輝きや社員の表情、地域との結びつき。決算書の数字に表れない部分にこそ未来の可能性が宿っている」と強調しました。
事業性評価と簿外資産 〜未来を見抜く視点〜
今回の講演の中で新田氏が強調したのは「事業性評価」という考え方です。財務諸表や格付けに依存するだけではなく、企業の未来をどう見抜くかという視点が不可欠だといいます。
決算書は過去の成果を写す鏡に過ぎません。未来を見通すには、土壌や根にあたる「簿外資産」に目を向ける必要があると新田氏は説きました。簿外資産とは、従業員の力(従業員資産)、顧客との関係(顧客資産)、地域との結びつき(社会関係資産)、そして経営者自身の資質(経営者資産)など、数字では表れない経営資源のことです。これらこそが次の果実を実らせる源泉だと新田氏はいいます。
講演では、決算書上は赤字続きで格付けも低い企業が、従業員の士気と顧客からの厚い信頼を力に、数年後には見事に再生を果たした事例なども紹介されました。「数字だけを見れば支援は難しいと判断されがちですが、企業の潜在力をどう評価するかが大切なのです」と語るその言葉に、会場の経営者たちは大きくうなずいていました。
一方で、簿外資産を評価することの難しさにも言及されました。定量的な基準があるわけではなく、評価する側の経験や感性に左右されやすいからです。「土壌、木の根を見るというのは、数値化できないもの、感覚的なものですか?」というメンバーからの質問に対し、新田氏はこう回答しました。
「数値化をあえてしなくてもいいと思っています。ただ、できるならしたらいいです。たとえば第一勧信では、地域の祭りへの参加回数をゼロから年間600回にまで増やしました。祭りに参加することが地域との絆の全てではないですが、わかりやすい指標にはできるじゃないですか。それで、どれだけ地域のお祭に出たかというのも業績評価として認めるよということをアナウンスしたわけです。そうしたら、もう全店一斉に祭に出はじめました(笑)」
さらに第一勧信では、創業50周年を機に各店に予算を割り当て、地域や顧客の要望に応える施策に充てた事例も紹介。これらは「簿外資産への投資」であり、管理会計上、会社の中だけは会計原則を無視して投資に置いてもいいのではと言います。
「数値というのはしょせん割り切りだけど、今まで出していなかった数値を持ち出す手はありますよね。視野を広げていくと打つ手は無限にあるんです。閉塞感があって真っ暗だと言っている人は視野が狭いだけだと私は思います。視野を広げれば、今はむしろチャンスです。」
簿外資産を評価する難しさを認めつつも、行動や貢献を定量化する工夫によって組織を動かし、未来を見抜く視点に結びつけることができる。その実践知が参加者に深い示唆を与えていました。
こうした「簿外資産の評価」という考え方は金融機関への提言であると同時に、中小企業経営者への問いかけでもあります。人材育成や顧客との関係づくりに投資することこそが、長期的な収益を生む「根っこ」になる。経営者自身が自社の「根っこ」を見極め、育てることが未来を切り拓く力になります。そしてそういった自社の価値をどう伝えるか、どのように信頼を築くか。数字で示すことはもちろん必要ですが、それだけでは伝わらない強みや可能性をどう表現するかは、すべての中小企業に共通する課題です。
幸せの4因子が示す組織の力
今回の講演では、金融の役割を「人と企業、地域をつなぐ絆」と捉える視点に始まり、数字によらない事業性評価の他にも様々なテーマや事例が共有されました。
・資金調達のフレーム:三つのカネ(自助・公助・共助)と四つの渡し方(負債・資本・売上・寄付)をどう組み合わせるか
・資金繰りの基本:運転資金は回転に合わせて更新、設備資金は償却期間に合わせる。赤字資金は原則避ける
・資本調達の注意点:「誰から資本を受けるか」が肝心。短期で騒ぐVCより、地域で腰を据えた資金が力になる
・組織づくりの技法:承認の言葉「さ・し・す・せ・そ」や、理念(パーパス)と裁量による自発性の引き出し方
その中で、「幸せの4因子」という切り口が印象的でした。
金融庁や財務局から「目利き力や事業性評価について話してほしい」と依頼されることが多いという新田氏。地域金融の基本指針に「事業性評価をしろ」「目利きが大事」と書いても、彼ら自身が実際にはどういうことなのか分からないからだと言います。50年にわたり中小企業融資の現場にいて、何千人もの経営者と会ってきた新田氏は、その経験から社長に会って2時間も話をすれば、その会社にお金を貸していいかどうかは大体分かると言います。ですが、それでは当然相手は納得しません。
そこでどう説明すればいいのかと考え抜いた末に、自分なりに「この四つのポイントだな」と整理したところ、後からそれが「幸せの4因子」と言われるものと重なっていたことを知ったのだそうです。
1. やってみよう(自己実現)
2. ありがとう(人とのつながり、感謝)
3. なんとかなる(前向きな楽観性)
4. ありのままに(自己受容)
新田氏は「この4因子が満たされている人や組織ほど、チャレンジ精神が高く、生産性も向上する」と語ります。
例えば、「やってみよう」が欠けている組織では、新しいことに挑戦する社員が育たず、次第に成長力を失ってしまいます。一方で「ありがとう」が組織に根づいていると、社員同士の関係性が強まり、困難に直面しても支え合える風土が生まれる。「なんとかなる」という前向きな空気は、不確実な時代において挑戦を続ける力になり、「ありのままに」が尊重される環境では、多様な人材が力を発揮しやすくなるのです。
経営者との会話の中でこの4因子を感じられるかどうか。会計の数字では見えない、組織の健全性や成長力を知る手がかりとして、経営者自身もまた自分や自社を振り返ることができるのではないでしょうか。
全国に広がるスモールサン・ゼミの輪
スモールサン・ゼミは、今回ご紹介したTOKYOをはじめ、全国各地で毎月開催されています。地域ごとに特色は異なりますが、「中小企業を元気にする」という共通の理念のもと、経営者が学び合い、共に成長していく場であることに変わりはありません。
ゼミTOKYOも、この9月から新たな期がスタートしました。これまで参加してきたメンバーに加え、新しい仲間を迎えて再び1年間の活動が始まります。毎月の講師講演や自社発表、そして会員同士の交流を通じて、経営の知恵と人脈を広げられる貴重な機会です。
スモールサン・ゼミには、初めての方でも気軽に参加できる「体験参加」の制度があります。「どんな雰囲気なのか知りたい」「講演や発表を実際に聞いてみたい」という方は、ぜひ一度足を運んでいただきたいと思います。
経営の現場は日々変化し、答えのない課題に直面することも少なくありません。だからこそ、一人で悩むのではなく、仲間と共に学び合える場所が必要です。今回のゼミTOKYOでの学びも、その大切さを改めて実感させてくれるものでした。興味を持たれた方は、ぜひ次回のゼミに体験参加してみてください!