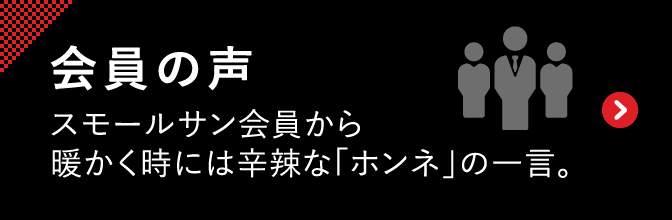<
山口恵里の“現場に行く!”2025年8月号
「第69回:株式会社ミツイバウ・マテリアル」
皆さん、こんにちは!スモールサン事務局の山口恵里です。
「山口恵里の“現場に行く!”」第69回は、三重県松阪市にある株式会社 ミツイバウ・マテリアルの代表取締役社長、三井陽介さんにお話をお聞きしました!
ミツイバウ・マテリアルは1951年創業で、鍋ややかんの物々交換から始まり、ガルバリウム鋼板の屋根や外壁材といった鉄鋼二次製品の卸売業、製造業、さらに施工へと時代に合わせて進化を続けてきました。
かつては超ブラックだったという社内の劇的な改善・改革、そして外国人材の育成と戦力化、さらに彼らのためのベトナム現地法人の設立など、「社員の幸福」を一番に掲げた取り組みで地域を代表する企業へと成長されてきました。
同社の創業からの歩みと、三井さんの人や地域を活かす未来戦略に迫ります!
【会社概要】
会社名 株式会社ミツイバウ・マテリアル
所在地 〒515-0104 三重県松阪市高須町3460番地125
代表者 代表取締役社長 三井陽介
設立 昭和49年(1974年)11月19日
従業員 66名(2025年3月20日)
事業内容 金属系外装建築資材・環境商品・住宅設備機器・建材などを三重県内全域のユーザー約500社に製造・加工・販売・施工している
URL https://mitsuibau.com/
創業から74年、進化を続ける「金属系建材の総合企業」
山口:三井さんは三代目でいらっしゃいますね。
三井:はい。創業は1951年に私の祖父がしています。なので、今年で創業74年目になります。最初は鍋ややかんを販売していて、大阪に仕入れに行って物々交換みたいな形でやっていたようです。たとえば食料を持って行って鍋ややかんを手に入れて、地元で売る、みたいな。最初は完全に卸売業で、そこから住宅設備とか、鉄の釘やなまし線などの建築資材に移っていきました。その後、やはり卸売だけではなかなか商売が…ということで、父の代になって製造業を始めました。工場を建て、仕入れた鉄のコイルを加工して、鉄鋼二次製品を製造するようになりました。
山口:ガルバリウム鋼板というのは鉄の原材料名なんですね。
三井:そうです。昔は亜鉛鉄板などでしたが、今はガルバリウム鋼板というものが主流になり、金属製の屋根材や外壁材に使用されています。この事務所の壁も見た目は木に見えますけど、木目の模様を入れてあるだけで全部鉄です。そういった鉄の屋根や外壁材の製造メーカーという立ち位置で、現在はそれがメイン業種になっています。大手メーカーさんのOEMも、自社オリジナルの商品も両方取り扱っています。それに加えて卸売、問屋機能も持っていて、いろんなメーカーさんの商品を仕入れて、地元の職人さんに卸すこともしています。
父の代からは、施工も少しずつ請け負うようになりました。ただ、やっぱりお客さんとバッティングしないようにという配慮もあって、当時は施工は控えめでした。
山口:では、本格的に施工をやるようになったのは三井さんの代からなんですか?
三井:そうですね。私が戻ってきたのが2010年なんですが、その頃は物販が8割、工事が2割くらいの割合でした。でも、物販だけでは厳しくなってきたのと、職人さんが減ってきていたということもあり、これからは付加価値として施工管理もしっかりやっていく必要があると思ったんです。それで施工管理といった資格等もその頃から積極的に取り始めました。いつも建材を買っていただいている職人さんに声をかけて、施工もそのお客さんにやってもらおうという形に変えていきました。私が戻ってきた頃ってリーマンショック直後で一人親方が増えている時代で、彼らは保険に入っていなかったり、職人さんによって品質がバラバラだったりなど色々な問題があるんです。なので、当社が施工を請け負った場合は、当社で保険をかけてちゃんと職人さんの安全を守りますと。また、元請けさんに対しては、我々がちゃんと品質を管理しますと。
山口:持ちつ持たれつの協力体制なんですね。
三井:はい。私たちは職人さんの仕事を取りたいのではなくて、職人さんとの協力体制で一緒に地域の仕事をやっていこうと。最初は29社からスタートしたのですが、口コミで広がって、今は70社近く加盟してくれています。実は物販の売上はここ十何年あまり変わっていなくて、この施工の売上が伸びたことで全体の売上が倍以上になっています。今の売上でいうと、もう半分強が施工請負になっています。
外国人材との共創で「労働力」から「戦力」へ
山口:御社は外国人材の活用でも先進的な取り組みをされていますよね。最初に実習生を受け入れたのはいつ頃だったんですか?
三井:実習生自体は、もう20年以上前、父の代から工場にはいたんです。でもその頃はいわゆる単純労働者という扱いで、3年で国に帰ったらまた別の実習生を採用してというのが前提でした。お蔭様で施工の仕事は順調に進んでいましたが、施工現場で人を集めるのが年々追いつかなくなっていきました。屋根の長さが50メートルとか100メートルとかの大きな現場が増えてきたんですが、その時に人が集まらないんです。それで、当社の営業が一緒に現場に入ったりしていたんですが、本来営業の仕事ではないんですよね。
山口:それはそうですよね・・・。
三井:それで2020年頃ですね。ちょうど建設業での技能実習生の受け入れ基準の強化など色々あったタイミングで、当社で技能実習生を採用して、職人さんをサポートすることにしたんです。当時協力会社さんは50社くらいで、それだけいれば助けて欲しい人もいるだろうと。人を採用するには保険に入れなきゃいけないとか色々な法規制があって、人件費がかかるから職人さん達はなかなか人を雇えない。でも、当社でそれをやってくれるなら、協力会社の人たちからすればただ助かるって話なので、うちがいいなら取り敢えずやってみるかという感じで始めました。
山口:とはいえ言葉の壁もありますし、大変だったんじゃないですか?
三井:そうですね。最初は私も一緒に現場に行ってたんですが、「言葉も通じないしどうなの?」という話をされることもやっぱりありました。それで、私はまず仕事よりも先に日本語を覚なさいと実習生にはずっと言っています。日本語さえ覚えてしまえば、周りが変わるんですよ。言葉が通じれば周りは仕事を教える気になるし、言葉が分かれば当人ももっと仕事を覚えることができる。
山口:そこから外国人材の教育方針が変わっていったんですね。
三井:彼らを「労働力」としてではなく「戦力」として育てたかったんです。私は2018年に代表になったんですが、2021年に完全に私が代表ひとりの体制になりました。それで、そのタイミングで、外国人材にもきちんと昇給制度を導入しました。日本人社員の場合、最初の頃は1年目、2年、3年目と社歴で昇給させるので、外国人材もそれと同じように昇給させるよと。基本給というベースが上がれば残業代も上がるので、長くいればより稼げる仕組みをつくりました。また、日本語のレベルに応じた「日本語手当」も導入しました。こちらが「日本語を覚えなさい」と言ってるのに、それに対して対価がないのでは誰も覚えませんからね。日本語能力試験のN4(基本的な日本語を理解することができる)ならいくら、N3(日常的な場面で使われる日本をある程度理解することができる)ならいくらと段階的に月給を上げる形で設定しました。お金がたくさん欲しいなら、日本語を勉強して長く働くのが一番だよと。
山口:やる気が出ますよね。
三井:それだけでみんな勝手に勉強し始めました(笑)。結果、それまではN4取るのが精一杯だったところから、現在はN1(幅広い場面で使われる日本語を理解することができる)を取った子まで出ました。N2(日常的な場面で使われる日本に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる)も2人、N3はゴロゴロいます。
山口:ホテルとかの接客業ならまだしも、建設業でN1は本当にすごいですね!
三井:だから皆、会議でも私の言ってることとか全部ちゃんと理解していますよね。社歴も一番長い子が特定技能で8年目になります。逆に日本人の子には「もう日本人というアドバンテージはないよ」と話しています。だって彼らも日本語ペラペラなんだから、仕事の能力が高い方が昇給するし、管理職にもなっていく。それが当たり前。実際、外国人財にも役職をつけていますし、管理の仕事も教えています。
“人のため”の海外展開でベトナム現地法人を設立
山口:現地法人をベトナムに設立されたのも、そうした流れの中で?
三井:そうですね。最初は、2018年に会長が「ベトナムに会社をつくる」と言い出したんです。自分のお金でやると言うし、正直その時は「第二の人生でやるのもいいんじゃないか」くらいの感覚でした。ところが、ベトナムの実習生の子たちと面談した時に、「社長ベトナムに会社つくるんですか?」って皆質問してくるんです。それで話を聞いたところ、皆いい会社で働けて満足していると。で、ベトナムに戻ってもいい会社に就職したいし、せっかく学んだことも活かしたい。本当にベトナムに会社をつくるんなら、そこで働きたいと言い出したんです。とは言っても、現地で会社なんてすぐにつくれるもんじゃないし、最低でも5年くらいかかる。あと5年間ここで働く気あるの?と聞いたら、「いや全然働きます!」と。彼らがそう言ってくれるなら、むしろちゃんと事業計画を立てて会社として出資してやるべきなんじゃないかと考え直したんです。
山口:実習生の人たちの声で風向きが変わったんですね。
三井:私は会社の基本方針に「社員の幸福」というのを掲げているのですが、実習生たちの幸福ってこういう事なんじゃないかと思ったんです。それから市場調査とかを始めて、彼らとも「サポートはするけど現地でやってくのは貴方達なんだから、向こうの社長は貴方達の誰かがやらなきゃいけないよ」という話もしました。ただ単に仕事ができるだけじゃダメで、管理とか教育のこととか全部必要だからねと。それと、向こうでも日本語能力試験の手当はつけると約束しました。
山口:ベトナムでも手当がつくんですか?
三井:はい。N1まで取る子が出てきたというのは、それもあっての嬉しい誤算でしたね。私はもともとN3でもいいと思ってたんです。まさかN1取るとは思ってなくて、まあまあな金額に設定しましたから(笑)。そういう感じで、全部がトータル的にいい方向に動いたんだと思うんですけど、今年2025年1月にようやく現地で有限会社ミツイバウ・ベトナムを設立できました。
山口:有言実行ですね。
三井:ただ、ベトナムってちょっと特殊で、まず事務所を借りないと会社の申請ができません。さらに工場用地を取得しないと製造業として申請できないんです。でも工場用地をいきなり買うのはリスクがあったので、まず事務所を借りて商社として設立しました。今は土地の交渉中で、契約ができたら製造業を申請して、業種形態を変えてやっていこうというところで、まだ本当に動き出したばかりです。私も頻繁にベトナムと日本を行き来していて、ちょっとずつ進めていっているというのが現状ですね。
山口:コンサルは入れてないんですか?
三井:現地の信頼できるパートナーはいます。長年うちの実習生を面倒見てくれていたベトナム人の子なんですが、故郷のバクザン省に日系企業を誘致したいという思いを持っていて、それなら一緒にやろうと。バクザンはハノイから1時間半くらいの場所で、隣のバクニン省は日本企業がたくさん進出していて、今工業団地がすごい勢いで増えています。でもバクザンはまだ20社程度で、次に来ると言われています。うちは工場の屋根が得意なので、それで今、日系企業と一緒にやれないかなと思って色々営業をかけたりしています。コンサルを入れてしまえば楽なんでしょうが、実際に自分で動くことで信用できる人脈を築くことができますし、そうした実体験を人に話すこともできます。私はベトナムで儲けようと考えているわけではないので、長い目で見て少なくとも10年以上、私の代では撤退しないぞという気持ちでゆっくりと進めています。
山口:こうしてお聞きしていると、全部「人のため」ですね。
三井:そうですね。でも、日本の会社にとってメリットがないかというとそんな事はなくて、まさに人材面でプラスになっていると思います。今の日本は最低賃金で韓国にも負けるでしょう。それで待遇の良くない会社も多いし、日本は人気がないんです。でもうちは賃金も改定しましたし、残業代も1分単位で払うし、寮だってちゃんと一人一部屋与えています。そして、国に帰ったとしても働ける会社がある。こういったことが安心材料になって、ベトナムの斡旋会社さんからも「日本は不人気だけど、ミツイバウだったら来るよ」と言われています。実際、日本人も外国人も毎年しっかり採用できていて、ほとんど辞める人もいないので、人手不足で困ることがなくなりました。
山口:外国人材の活躍と現地展開が、ちゃんとつながっているというのがすばらしいですね。
「社員の幸福」を軸に進めた改革とDX推進で「ブラック企業」からの脱却
山口:「社員の幸福」という基本方針が、垣根なくベースとしてしっかり根付いていますね。
三井:でも、実は私が戻った当時は超ブラック企業だったんですよ。
山口:えっそうなんですか?
三井:サービス残業は当たり前で、平均残業時間は60時間超え。ちなみに営業赤字で社員が怒って事務員さんは泣いてるみたいな。離職率は9割で、最短2時間で辞めた人もいました(笑)。当初先代からは営業課長で戻って来いと言われたんですが、私はまず平社員で工場から始めて現場を全部署回ったんです。すると、どこもとにかく「見て覚えろ」の世界。さらに超アナログで、ヒューマンエラーの嵐。工場に行くと手書きの伝票が流れてくるわけです。加工成形で1mm単位で注文を聞いてくるのに、そもそも0か6かも分からない。それでいちいち聞き直してって、もう時間の無駄ですよね。
山口:そこからどうやって変えていかれたんですか?
三井:とにかく人を採らないと未来はないと思って、中途で一人ずつ採用していたんですが、まあ一人採っては辞めての繰り返しです。先代は人を採用して売上上がらなかったらお前ら給料ないぞみたいことを言うんですが、私は当時の幹部社員と相談して、とにかく人を採用すれば売上は上がるからと言って、新卒で4人採用することにしました。それまで若手がおらず話し相手もいなかったので、同期をつくるようにしたんです。3年間で12人採用し、そのうち3年以内で辞めた子は一人だけで、そこからグッと雰囲気が変わりました。ちょうど建築バブルのようなものが起きていたこともあって仕事が取れていましたから、その利益をIT投資や設備投資に回してアナログな環境の改善も進めました。それでまた社内の雰囲気が変わって・・・という繰り返しです。
山口:15年をかけて少しずつ、でも劇的に改革されたんですね。
三井:2013年に課長になって、そこで「社員の幸福」を基本方針の一番上に持ってきました。それで社員一人ひとりに「あなたの幸福って何?」と聞いて回ったんです。「給料を上げて」は分かってるので、それ以外のことで。そうしてヒアリングした内容から、お金のかからないところはすぐに改善して、お金のかかるところは採択しながら毎年一個成長させるというのを今でもやっています。それで社員専用のスポーツジムもつくったんですよ。プロ用のマシンを一通り入れて、シャワールームもあって、休みの日でもスマホでピッとやったら入れるという。お金がなかったので最初は見送ったんですが、2年前にやっと実現できました。
山口:めちゃくちゃ本格的なジムですね!
三井:そういった福利厚生の部分と、並行してIT化、DX化もやってきました。初めはお金がなかったので、アナログ業務を全部エクセルで作り替えたりしていって、社長になってからは三重県の中小企業で最初にRPAを導入してニュースで取り上げられたりもしました。(RPA:ロボティック・プロセス・オートメーション。人がパソコン上で日常的に行っている定型業務を、ソフトウェアロボットを使って自動化するもの)現在は新しい基幹システムも完成して運用できていて、今はそれと連動させた見積システムを開発しています。最終的には、全ての業務がパソコンとスマホのアプリでできるようにするのを目指しています。
山口:本当に劇的な変化ですが、社内での反発はなかったんですか?
三井:最初はすごくありましたね。当時は年齢的にも上の人ばかりでしたし、「手書きの方が早いし楽だ」って。そんなわけないんですけどね。実際最初は力技でとにかく一回やってみようと、取り敢えずやってみてから考えようと言っています。採用もITに詳しい子を採るようにして、その子達には「うちはITリテラシーが低いから、悪いけど聞かれたら何回でも教えてあげて」と話しました。それで自分が使えるようになると、コロっと手のひら返すんですよ(笑)。「社長これめっちゃ便利やん、もっと早く使っておけばよかったわ」って(笑)。半分が使い出したらもうこちらの勝ちです。みんな使いだしたら「俺もちょっとやろうかな」ってなるし、やってみたら案外使えるんですよ。うちが基本的に自社開発にこだわってるのはそれが理由で、誰でも使えるような操作性で、かゆいところに手が届かないと続かないと思っているからです。
結果として業務効率が劇的に上がりました。今は19時以降会社には誰もいませんし、サービス出勤もない。有休消化率も向上しました。うちは年間休日105日で、求人媒体からは最低110日はないとダメだって言われるんですが、私は有休消化率100%の方が優先だと社員には言ってるんです。だって決められた休みより、好きに休める方がいいじゃないですか。実際好評で、うちは社員が持ち回りでブログを書いてるんですが、最近は旅行のことばっかりです(笑)。
山口:ブラック企業からの脱却どころか、正反対の会社へ変貌を遂げてますね。
人と地域を活かす持続可能な未来戦略
山口:最後に今後の展望などをお教えいただけますか?
三井:今年2025年1月に「ミツイバウ・ホールディングス」を設立し、その傘下に「ミツイバウ・マテリアル」、その下に「ミツイバウ・ベトナム」が入る形でホールディングス化しました。ミツイバウ・マテリアルの中では、一級建築士事務所と太陽光の合弁会社があります。でも業務を多角化しようというわけではなくて、全部本業でやっていたことを法的にもきちんとできるようにしようという感じです。例えば、今施工は大手の仕事も増えてきていて、大手さん相手だとやっぱり図面の精度も求められるんです。でも普通に採用しても設計士さんは来てくれないので、それなら設計事務所をつくった方がいいと。実際にそれで何名か入ってくれて、そうするとお客さんの増改築の相談なんかも自社で受けれるようになります。
山口:こうしてお話を聞いていると、次の展開はM&Aなのかなという感じがしますが。
三井:M&Aはめちゃくちゃ言われますね。ただ、うちは人には困ってないですし、M&Aをするとその会社を管理しなきゃいけないですよね。今もう社員が80人近くいますし、さらに拠点が違ったら余計管理できないと思ってるんです。なので、M&Aで規模を広げるよりも、信頼できる仲間や地域の職人さんと共存共栄していくほうがうちのやり方に合ってると思っています。実際に県外の同業他社さんとも助け合って、お互いの地元案件を協力してこなしています。
山口:M&Aで自社を大きくするよりも、地域の中で共存しながら自分の業界や業種でやれることをやっていくと。
三井:その為にもやはり信頼関係が欠かせないですよね。お客さんや職人さんも高齢化していますので、「もうできないから頼む」と仕事を引き継ぐというケースも増えています。私は「下請け」という言葉が一番嫌いなので、社員にも「協力会社」という呼び方を徹底して、対等で長続きする関係を築くよう心がけています。いい関係性の相手とは、いい仕事ができます。その土台があるからこそ、社員も気持ちよく働くことができる。
今実は経営指針なども一度見直していて、これができたら皆で10年ビジョンをつくろうと思っています。私がやりたいことが皆とイコールであれば一番いいんですけど、やっぱり彼らがやりたいことを叶えてあげた方がいいなと思っているので。私自身はあんまり規模を追っていないなくて、東海一番くらいは目指そうかと思っていますが、結果は後からついてくると思っているタイプなので、やっぱり松阪市で「ミツイバウに就職して良かった」と言ってもらえる会社を皆とつくっていきたいと思っています。
山口:本日はありがとうございました!