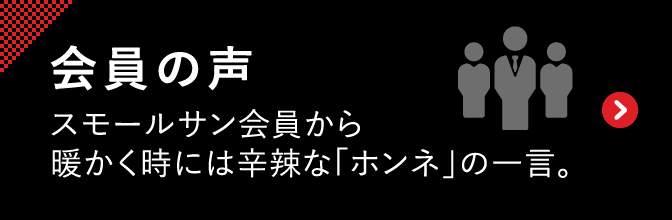<
山口恵里の“現場に行く!”2025年7月号
「第68回:
松阪市中小企業ハンズオン支援事業 最終報告会レポート」
皆さん、こんにちは!スモールサン事務局の山口恵里です。
去る5月15日、松阪市が実施する令和6年度中小企業ハンズオン支援事業の最終報告会が行われ、スモールサンも共に支援をさせて頂いた株式会社柳屋奉善の岡一世氏が発表をされました。
また、同日に開催された令和7年度の支援事業公開審査会では、5事業者の応募からスモールサン・ゼミMATSUSAKAメンバーである株式会社ミツイバウ・マテリアル(代表取締役社長 三井陽介氏)が選出されました!
そこで今回は、最終報告会と公開審査会のレポートをお届けします!
450年の歴史と「御茶席用 老伴」復刻の軌跡
天正3年(1575年)創業の柳屋奉善は、三重県松阪市で450年の歴史ある老舗の和菓子屋さん。特に代表銘菓「老伴(おいのとも)」は、天下人の織田信長や豊臣秀吉からも高く評価され、松阪の礎を築いた戦国武将である蒲生氏郷公に献上された由緒を持ち、長年地域に愛されてきました。
2023年度、同社は松阪市の「中小企業ハンズオン支援事業」に採択され、自社のルーツを改めて見直し、その中核商品である「老伴」の復刻に取り組みました。もともとの「老伴」は、お土産菓子として紅麹と手亡豆を使った現在の製法ではなく、戦国期には献上菓子として当時とても高価だった白小豆や本紅を使用し、味わいも見た目も現在とは異なるものでした。今回の取り組みでは、松阪市の協力のもと古い文献を紐解き、当時の素材や製法に可能な限り忠実に再現するかたちで「御茶席用 老伴」の開発が行われました。
本紅や白小豆、伊勢米など、当時の製法に近づけるための素材探しは困難を極めましたが、千利休の高弟「利休七哲」にその名を連ねる氏郷公を「戦国茶人」と表現し、その戦国茶人自らが改良に携わったという高級茶菓子としてのこだわり、そういった「物語のあるお菓子」づくりを通して、老伴というブランドの再定義に挑みました。完成した復刻版「御茶席用 老伴」は初釜式で披露されました。なんと京都にある千利休が建てたという国宝「待庵」でのお茶席でも使用され、カラフルな最中から自分の好きな色を選び、客自ら最中に羊羹を乗せて食べるという演出のもと提供されたそうです。店頭販売では、あえて販売期間や数量を限定にし、一期一会の特別な体験性を演出することで、大きな反響がありました。
岡さんは「長く続いてきたものに意味があると信じるだけでなく、なぜ続いたのか、なぜ今の時代にも通じるのかを伝えることが大切」と語ります。老舗の“伝統のアップデート”ともいえるこの取り組みが、松阪という地域の歴史と未来をつなぐ橋渡し役となるのではないでしょうか。
地域連携の広がりと海外展開
ハンズオン支援を通じて、地域との連携や海外展開への試みにも積極的に踏み出しました。
まず地域連携の一環として行われたのが、晦日市という柳屋奉善が毎月開催しているマルシェでの限定コラボ商品「さわもなか」の開発。
江戸時代、松阪の商店街は「餅街道」と言われ、伊勢参りの旅人達は様々な名物餅を楽しみ、餅百珍には数々の名物餅がリストアップされています。そんなお伊勢参りで賑わっていた頃のように松阪をもう一度盛り上げたいという構想のもと、「さわ餅」という銘菓を製造している老舗の山作とコラボレート。山作の「さわ餅」と柳屋奉善の「鈴最中」を組み合わせた、限定コラボ商品を開発しました。
当日はあいにくの雨にもかかわらず、多くの来場者が足を運び、予定数30個が即完売。その後20個を追加し、計50個を完売する盛況ぶりを見せました。
続いて、海外展開では、柴沼醤油インターナショナルの支援を受け、柳屋奉善がトルコ・イスタンブールへ赴いた取り組みが報告されました。2024年は日土国交100周年という記念の年にあたり、現地でのイベントやプロモーション活動に絶好の機会となりました。
視察の一環で訪れたのは、現地の人気寿司チェーン「Sushico」のイベント。ここでは、日本らしい抹茶や柚子に加えて、トルコの食材である無花果(いちじく)と柘榴(ざくろ)を使った羊羹をあわせた老伴を提供しました。特に無花果の味はトルコの人々に馴染み深く、現地来場者から好評を博しました。
その他にも複数の商社を回り、現地市場における輸出展開の課題も浮き彫りになりました。賞味期限が1年未満では扱いが難しいことや、遺伝子組換えに関する検査など、まだまだ同社にはハードルが高い部分があることも分かり、今後は取り組み方も工夫して変えながら挑戦していきたいと語りました。
今後の課題と展開
御茶席用老伴については、現時点では郵送の対応ができていないことから、今後は発送体制を整えることが課題となります。
この課題をクリアすることで、今後は百貨店の銘菓コーナーや京都の茶道関係店舗への販路拡大を目指すことができるようになります。また、地域コラボについても、今後も餅に限らず様々な地域の特産品とのコラボレーションを積極的に行っていくことで、話題性をつくり、同社はもちろん地域のブランド価値を高めていく意向が語られました。
また、海外展開についても、海外出張の多い日本企業へ向けて、老伴とその発生商品を「日本のお土産の代表」として展開できるようにPRしていきたいと語りました。
講評と質疑応答を通じた未来への問い
成果報告の後には、審査委員による講評や質疑応答が行われました。その一部を抜粋してご紹介したいと思います。
審査委員「昨年の審査では“あまりわたわたしないように、ちゃんと歴史を他の人にも伝えられるように”というコメントをさせていただきましたが、今年はその歴史をしっかり活かした活動になっていて本当に感心しています。特に、ものづくりの視点から見ても、今回の製品は非常に良い出来だと思います。今の製造ラインでは難しい形だと思うので、人気が出た場合には製造方法や工程を改めて考えてもらえればと思います。」
審査委員「450年を経て、次の500年に向かっていくタイミングとして、このハンズオン支援は非常に意味のあるものでした。何よりも18代目の意識改革が大きかったと感じます。この1年で、どれほど自分自身が変われたと感じているのか、改めてお聞きしたいです。」
岡氏「実際、意識が変わってきたという実感は大きくありまして、やはり今回自社の起源や歴史と向き合ったことによって、当社が掲げてきた『柳屋奉善』という社名を自分の中でストンと落とし込めたというのが一番大きな変化かなと思います。柳屋というのは“柳の葉のように時代に順応する”、奉善というのは“善を奉る”という意味があります。社名の意味を改めて考え、これからはお茶の文化やお菓子の意味をもっと真剣に捉えて学び、伝えていきたいと思っています。」
審査委員「素晴らしいなと思ったのは、やはり老伴の歴史を調べるというところから入れられたこと。この支援の内容が非常に素晴らしいなと思ったんですけども、今回この全ての支援の中で、最も時間をかけて取り組んだのは何だったのでしょうか?」
岡氏「やはり『御茶席用 老伴』の開発です。まず本紅という素材のことを調べるところから始まり、東京の紅ミュージアムまで足を運び、昔ながらの製法を持つ企業から素材を入手しました。その調査と準備にもかなりの時間が必要で、ハンズオン支援のおかげでじっくり時間を使って取り組むことができたと思います。」
審査委員「なぜ御社が450年も残ってきたのか。その理由をまだまだ解き明かす必要があると思います。ただ味や食感だけでなく、“なぜこの味が残ったのか”“なぜ続けることができたのか”という本質的な問いに、感覚だけでなく言葉で答えられるようになっていってほしいなと思います。」
講評と質疑を通じて、老舗の歩みをどう次代に繋げていくか、そしてそれをどう伝え、実行していくかについて多角的な意見が交わされました。
令和7年度 松阪市ハンズオン支援
〜建設業の人手不足に挑むミツイバウ・マテリアルの挑戦〜
さて、同日に公開審査が行われた2025年度松阪市ハンズオン支援事業に選ばれたのは、建築資材の製造・卸を手がける株式会社ミツイバウ・マテリアルでした。同社が掲げたのは「外国人労働者の受け入れ体制整備」を中核に据えた、建設業界における海外人材育成と定着支援の包括的な仕組みづくりです。
プレゼンでは、10年前に設立された地域の職人団体「安全衛生協力会」に始まり、すでに68社が加盟する地域施工ネットワークが紹介されました。人手不足が深刻化する中、同社は外国人実習生・特定技能者・留学生の雇用と育成に先進的に取り組み、技術教育、日本語教育、保険対応など、現場に即した支援体制を整備してきました。
実習生への待遇改善や、役職登用制度の整備、日本人社員と同等の待遇導入など、“安い労働力”としてではなく人材の“専門職化”を進めた結果、社員の定着率も向上し、採用も安定して続いているそうです。また、ベトナムに現地法人を設立し、日本で培った技術を現地に還元する循環型の国際人材モデルを目指していることも報告されました。
プレゼン後の質疑応答では、委員から「全国展開可能なビジネスモデル」として高い関心が示されました。特に「建築現場を支える多国籍人材ネットワーク」の実現性と、それを下支えするマニュアル・教育体制の整備に注目が集まりました。他企業へのノウハウ還元や、外国人雇用に関する仕組みのモデル化といった社会的波及効果への期待も高いです。
コミュニティと雇用をつなぐ“人材インフラ”へ
ミツイバウ・マテリアルの挑戦は、単なる人材確保を超えて、地域社会と企業をつなぐ“人材インフラ”構築の取り組みでもあります。
社長は「外国人雇用の実態は、まだ多くの中小企業がノウハウ不足で足踏みしている」と指摘。だからこそ、同社が率先して実績を積み上げることで、地域に“雇用の自信”を伝播させたいと語りました。
支援の具体的な展開としては、①職人と建材を統合した施工チームのモデル化、②ベトナムでの職業訓練校・工場建設構想、③多国籍人材の社内マネジメント支援制度の整備、④留学生の新卒採用とキャリア定着支援、などが挙げられます。
「社員面談を通じて“毎年ひとつ、自分に宣言を課す”という制度も導入した」と社長は語りました。社員一人ひとりが自発的に学び、成長できる仕組みが、組織の持続力を高めている。その結果、社員紹介による入社が増加し、直近3年の定着率は100%を維持しているといいます。
審査委員長・西村氏は、「日本の建設業界における人材モデルの転換点になる可能性がある」「上場を見据えるレベルの挑戦だ」と評価され、今後の展開に大きな期待を寄せられました。
そこで次回の別刊ニュースでは、ミツイバウ・マテリアル代表取締役社長の三井陽介さんに取材し、同社の人材育成・人材活用の取り組みについて詳しく取り上げたいと思います!